大学受験で第一志望合格が叶わず、大学院受験で学歴ロンダリングをしようと考えている方もいると思います。他大学から東大院に進学した私が、学歴ロンダリングで院進することの就活への影響やメリット・デメリットについて説明していきます。
学歴ロンダリングとは
学歴ロンダリングとは、学部時代の大学よりもレベルの高い大学院に進学することで、最終学歴を上書きすることを言います。
例えば、学部が地方国公立で、大学院で旧帝大に進学する場合は学歴ロンダリングだと言われることがあります。
一方で、特に日本の学歴社会において、学歴ロンダリングは一種のキャリアアップの方法であると肯定的に見なされることもあります。
学歴ロンダリングのメリット
学歴ロンダリングでレベルの高い大学院に進学することには多くのメリットがあります。
ネームバリューが得られる
東大などのトップレベルの大学院に進学することで、その大学のブランド力を手に入れることができます。これにより、就職活動や社会的な評価において有利になる場合があります。
学歴コンプレックスが軽減される
学歴に対するコンプレックスを持っている人にとって、レベルの高い大学院に進学することで大学受験のリベンジとなり、コンプレックスを解消する手段となる場合があります。
専門的な知識・スキルの習得
レベルの高い大学院では、より高度な専門知識やスキルを学ぶ機会が増えます。これにより、将来的なキャリアパスの幅が広がり、特に大手企業の専門職や研究職への道が開かれる可能性が高まります。
人脈の構築
優秀な教授や同級生と出会うことで、将来にわたって役立つ人脈を構築することができます。
特に東大のような大学では、非常に優秀な学生に囲まれる生活を送るだけでなく、幅広い分野で活躍する卒業生とのネットワークが期待できます。
学歴ロンダリングのデメリット
学歴ロンダリングには魅力的な要素が多いですが、デメリットもたくさんあります。
院試合格が(比較的)難しい
レベルの高い大学院に進学するためには、多くの場合、非常に難易度の高い院試に合格する必要があります。特に人気のある研究室や分野では競争が激しくなる傾向にあり、合格を勝ち取るのが難しい場合もあります。
内部生との差に悩むことがある
学部からそのまま進学してきた内部生との間に学力や研究の進捗状況に差が生じることがあります。
この差に悩み、研究が手につかなくなる可能性が考えられます。
研究が十分にできない
レベルの高い大学院では、研究の質と量が求められます。これに対応できない場合、研究が十分に進まないことが考えられます。
特に博士課程からの学歴ロンダリングの場合、卒業には学術論文提出という明確な成果が求められます。そのため標準年数で卒業できず、オーバードクターや退学となることも少なくありません。
経済的負担
大学院進学には学費や生活費がかかります。特に都市部の大学院では生活費が高く、奨学金だけでは賄いきれずアルバイトをすることになり、結果として研究時間を十分に取れなくなるなど負のスパイラルに陥る可能性も考えられます。
学歴ロンダリングの就活への影響
ポジティブな影響
ネームバリューの高い大学院を卒業することで、企業からの注目度が上がります。
実際、就活サイトにおいて大手企業からジョブオファー・ES免除などの優遇措置が届くことも多いです。東大院卒(見込み)という肩書きは大きな武器となり、学歴フィルターを突破する確率も高くなると考えられます。
ネガティブな影響
一方で、学歴ロンダリングを行ったこと自体をネガティブに捉える企業も存在します。
特に、学部時代の成績や活動が芳しくない場合、それが理由で学歴ロンダリングを行ったと見なされることがあります。また、ES提出の際には卒業した大学学部の記載を求められることも多いです。
そのため学歴だけでなく、もう1つ自分をアピールできるものがあると良いでしょう。
研究職志望の場合は、大学院での研究内容や成果をしっかりとアピールすることが重要です。
外資やコンサル志望の場合は、一定の研究成果+英語(TOEIC)があると有利になると思います。
まとめ
学歴ロンダリングには多くのメリットがありますが、デメリットや注意すべき点も多く存在します。
大学院進学を考える皆さんには、自分にとって最良の選択ができるよう、十分に情報収集を行い、慎重に判断してほしいと思います。


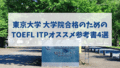
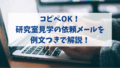
コメント