この記事では、令和4年度(2022年度)の東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端生命科学専攻の受験について書きたいと思います。
特に外部からの院試については情報が少なく、そのために受験の際に不安や困難を感じることも多いと思います。この記事が少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。
受験のきっかけ
将来的には専門性を活かした職業につきたいと考えていたため、漠然と「大学院進学はしたい」と考えていました。
ですが、学部時代の研究を大学院でも研究を続けることを考えると、自分が本当に興味を持てる研究をしたいと思うようになり、外部院試を検討することにしたのです。
受験を決めてからやったこと
まず、自分の興味に沿ってキーワード検索を行い、外部受験をする研究室を探しました。
大学受験とは異なり、大学院入試では国公立大学院を複数受験することができるので幅広く検討することができます。その結果として、以下の候補があがりました。
- 東大院 新領域創成科学研究科 先端生命科学専攻
- 東大院 工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻
- 京大院 生命科学研究科
- 東北大院 生命科学研究科
- 北大院 生命科学院 生命統合科学コース
- 東工大院 生命理工学院
中でも、私が一番興味関心があったのは東大院 新領域創成科学研究科 先端生命科学専攻の研究室でしたので,主にこちらの対策をしていくことにしました。
ただ,実際には複数合格をいただけたとしても辞退する必要があり、相手方の研究室の迷惑になってしまう可能性がある点には十分注意したいところです。
また、複数の研究科を受験することは体力的にも経済的にも大変です。そのため、乱れうちするのではなく、進学志望度の高い1~2つを受験するのが良いかと思います。
試験対策
外部院試をすることを本格的に決定したのは大学3年の7月頃でした。それから、以下のような対策をスタートしました。
- 大学院試説明会への参加
- 研究室訪問のメール
- 実際の研究室訪問
- 志望理由書・願書の作成
- TOEICの勉強
- TOEFLの勉強
- 基礎的な生命科学の勉強
- 専門科目の過去問演習
各対策の具体的な方法については別記事で紹介したいと思います。
特に、大学院試説明会はその研究科の特色や、各研究室の研究内容などを深く知ることが出来る良い機会です。少しでも受験する可能性がある場合には説明会に参加することをおススメします。
先端生命科学専攻の場合にはHPで説明会に関する情報が提供されています。

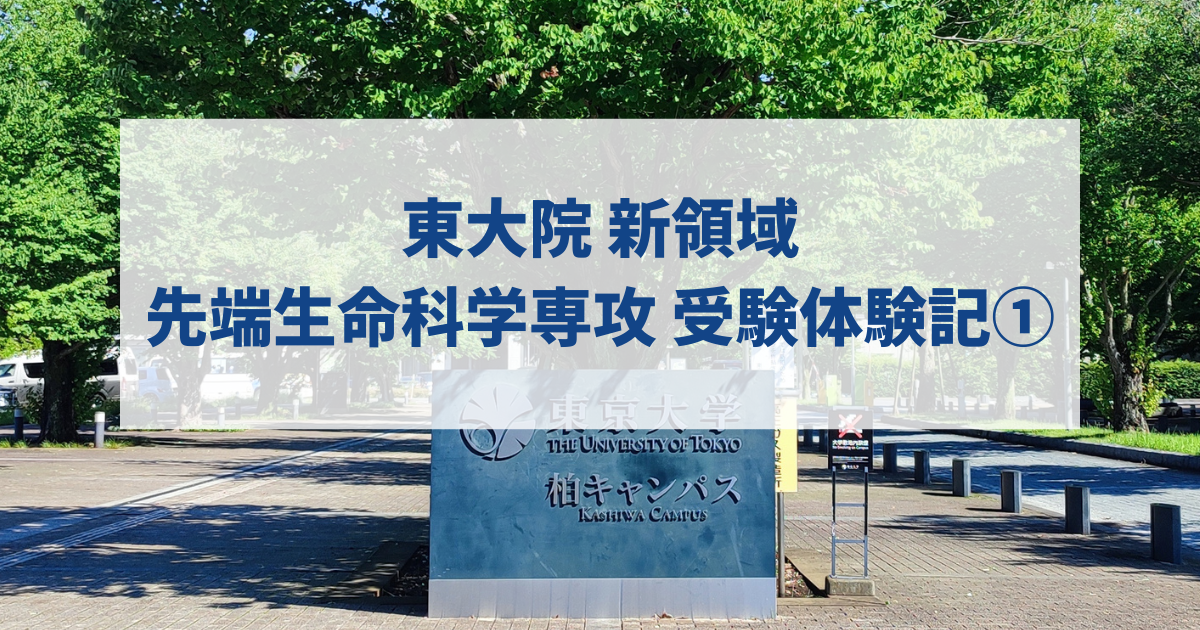

コメント